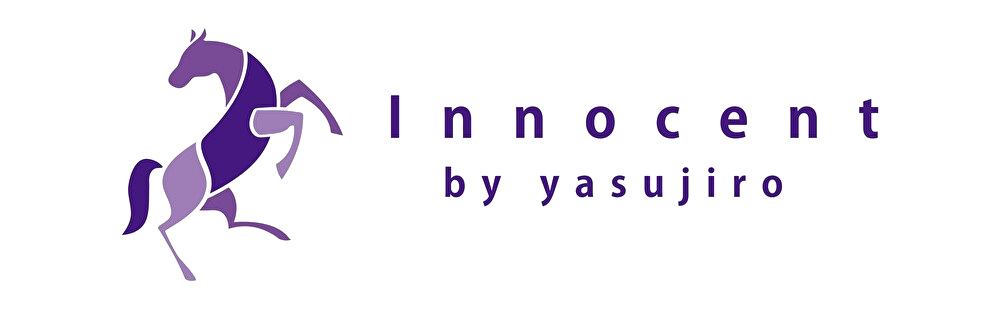2025/09/10 11:35
朝晩の空気に、少しずつ秋の気配を感じるようになってきましたね。
昨日、9月9日は「重陽(ちょうよう)の節句」でした。
3月3日の桃の節句や5月5日の端午の節句は、子どもの成長を祝う行事として広く親しまれていますが、重陽の節句は少し馴染みが薄いかもしれません。
けれども古来より「長寿」や「無病息災」を願う、とても大切な日とされてきました。
重陽の節句は、日本の五節句のひとつ。
菊の花を飾ったり、花びらを浮かべたお酒=「菊酒」をいただいたりして、健やかな暮らしを祈る習わしがあります。
起源には諸説ありますが、平安時代に中国から伝わったといわれています。
古くから奇数は縁起の良い「陽の数」と考えられており、その中でも最も大きな「9」が重なる9月9日を「重陽」と呼び、祝うようになりました。宮中では「菊花の宴」が催され、和歌を詠み交わすなど、優雅な文化も育まれました。
この日は菊だけでなく、旬を迎える栗ご飯や秋茄子を使った料理も欠かせません。秋の味覚とともに、自然の恵みをいただきながら節句を楽しむことができるのです。
日本には春夏秋冬の四季があり、それぞれに節句が結びついてきました。
こうした行事を暮らしに取り入れることは、単なる伝統の継承ではなく、日々をより豊かに、そして丁寧に過ごすことにつながるのだと思います。
きものもまた、四季を映し出す日本の文化です。節句と同じように、その時々の季節を楽しむ心を映し出す存在といえるでしょう。